- 吉野家ホールディングスが一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期的に開催
- 講習会は心肺停止や呼吸停止に対する対処法を学び、緊急時の対応力を強化
- 全従業員を対象に開催し、地域社会の健康と安全性向上に貢献
- 救急医療に精通した男性看護師が講師を務める
- 講習会は2023年以降15回実施され、延べ300名以上が参加
吉野家ホールディングス一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期開催












[株式会社吉野家ホールディングス]
[画像1: https://prtimes.jp/i/19432/370/resize/d19432-370-7078b98023fe298fbbe8-1.jpg ]
株式会社吉野家ホールディングス(代表取締役:河村泰貴、本社:東京都中央区)は、本社従業員および株式会社吉野家、…
吉野家ホールディングス一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期開催大切な人や周囲の人を守れる術を学び、緊急対応力を強化地域社会の健康と安全性向上に貢献吉野家ホールディングス2024年12月6日 11時00分 株式会社吉野家ホールディングス(代表取締役:河村泰貴、本社:東京都中央区)は、本社従業員および株式会社吉野家、株式会社はなまるをはじめとしたグループ会社の全従業員を対象に、心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期的に開催しています。 当社は、食材を製造加工する工場や「吉野家」「はなまるうどん」をはじめとした飲食店を全国で運営しています。工場は地域に雇用を創出して地域社会の発展に貢献し、店舗は地域で生活する皆様が健康的な毎日を送るために美味しくて健康な食事を提供することに尽力しています。そして、さらなる地域社会の健康を支える存在となることを目指して、当社グループの全従業員を対象に、心肺蘇生やAEDの操作方法を学ぶ一次救命処置講習会を開催しています。 日本では毎日6分に1人が心臓突然死で亡くなっています※。心臓が止まると15秒で意識を失い、4分で元に戻らない脳のダメージを負い、他の機能や臓器にも重大なダメージが残ることがあります。そのため、心肺停止または呼吸停止による緊急の場面では、傷病者の周囲にいる人が救急車や医師に引き継ぐまでに早期に適切な一次救命処置を施すことができると、救命の可能性が高まります。工場では多くの人が働き、店舗には多くの人が来店されるため、このような緊急時に遭遇する可能性は皆無ではありません。従業員が緊急時に居合わせた場合に適切な対応をするために、一般社団法人Nurse-Men(ナースメン)に所属する救急医療に精通した男性看護師が講師を務める講習会を定期的に開催しています。 ※公共財団法人日本AED財団より https://aed-zaidan.jp/knowledge/index.html 講習会は2023年7月以降、これまでに15回実施し、延べ300名以上が参加しました。2024年11月26日は千葉県船橋市において、千葉県にある吉野家店舗のエリアマネージャーや店長を対象とした講習会を開催しました。講習会では緊急時の実例から一次救命処置の有無によって救命率が異なることや、胸骨圧迫による心肺蘇生やAEDの操作方法などを学びます。その後、複数名のチームに分かれて心肺蘇生マネキンを用いた一次救命処置を模擬訓練して、緊急時の適切な対応を習得します。 参加した従業員からは、「救えるはずだった命を1人でも減らしたいと思った。(20代男性)」、「必要な場面に遭遇したら勇気を持って行動が出来る人になりたい。(30代女性)」、「生命を繋ぐ場面で勇気を持って行動できる自分でありたいと強く思いました。(50代男性)」などの感想が寄せられました。 なお、講習会に参加した当社の女性社員は実生活で一次救命措置が必要な緊急時に遭遇し、適切な対応を行うことで人命救助に貢献した実例も生まれています。今後も引き続き、全国で講習会を開催し、従業員に参加を促すことで、地域社会の健康と安全性向上に貢献できるよう尽力してまいります。 ※当社で開催した心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」の様子はYouTube( https://youtu.be/argssGvnutg )でご覧いただけます。 【一般社団法人Nurse-Men】 https://ns-men.com/ 看護師の中で男性は約1割程度。男性看護師の存在を世の中に認知してもらうために、全国各地で啓発活動を行う男性看護師チーム。「全国民が目の前の命を救える時代へ」をミッションとして、全国の企業や小中学校、高校、イベント会場で一次救命処置の体験会や講習を行う「命のバトンプロジェクト」を推進している。また、様々なイベント(フェス、祭り、催事、スポーツ大会、格闘技など)での医療チームとして携わる他、災害支援活動なども行なっている。このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報がありますメディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちらメディアユーザー新規登録無料メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。すべての画像種類その他 ビジネスカテゴリレストラン・ファストフード・居酒屋キーワード吉野家はなまるうどん救命地域安心安全健康AED緊急関連リンクhttps://youtu.be/argssGvnutgダウンロードプレスリリース素材このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできますトッププレスリリース株式会社吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期開催会社概要株式会社吉野家ホールディングスRSSURLhttps://www.yoshinoya-holdings.com/業種飲食店・宿泊業本社所在地東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート18階電話番号03-5651-8771代表者名河村 泰貴上場東証1部資本金102億6500万円設立1958年12月トレンド情報をイチ早くお届けPR TIMESを友達に追加PR TIMESのご利用について資料をダウンロード
全文表示
ソース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000370.000019432.html
吉野家の動画をもっと見る- 吉野家の朝食を食べた方に100円引きのクーポンを配布するキャンペーンは、新生活シーズンにぴったりのサービスだと感じました。朝食を吉野家でとることで、昼食や夕食もお得に楽しめるというのは魅力的ですね。吉野家の取り組みには、お客様の生活に寄り添ったサービス提供の姿勢が感じられます。
- 吉野家の「缶飯牛丼」が防災グッズ大賞の優秀賞を受賞し、販売数が130万食を突破したとのニュース、興味深いですね。防災意識の高まりに合わせて、セールも実施されているようで、家庭の備蓄や新生活の備えに役立ちそうです。缶飯の種類も豊富で、セット販売もあるので、一度試してみたいと思います。
- はなまるうどんの創業25周年を記念して、高松の最寄り駅が「はなまるうどん駅」となるなど、地元とのコラボレーションが素晴らしい取り組みだと感じました。さらに、香川県産小麦「さぬきの夢」を使用したうどんの提供も始まるとのことで、地元愛と品質へのこだわりが感じられます。はなまるうどんのこれからの展開に期待が高まりますね。
- 「超特盛祭」の開催は、吉野家ファンにとっては嬉しいニュースですね。特に新商品の「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」は、スタミナ満点で食欲をそそる一品だと感じました。吉野家の取り組みには、お客様へのこだわりとサービス向上の意欲が感じられます。
- はなまるうどんの新メニュー「ホタテ味噌バター」「豚肉味噌バター」は、赤味噌と白味噌が織りなす特製スープにとろけるバターが絶妙にマッチしていそうですね。特にホタテの上品な旨みが楽しめる「ホタテ味噌バター」は、贅沢な一杯として魅力的です。また、辛味噌入りのバリエーションもあり、辛いもの好きにも満足できそうです。寒い季節にぴったりの濃厚な味わいに、ぜひ挑戦してみたいです。
- 吉野家公式通販ショップで国産オーストリッチオイルを使用したスキンケアブランド「SPEEDIA」の全商品が販売開始されたとの情報を知りました。オーストリッチオイルの保湿効果や肌への優しさが強調されており、特に肌の潤いをサポートする成分が含まれている点が興味深いです。さらに、飲食業で働く人に寄り添った商品として「SPEEDIAハンド&ボディミルク」が開発されたという点も素晴らしいですね。吉野家のスタッフの声を反映させた商品が登場するというのは、消費者とのつながりを感じさせる取り組みだと感じました。
- ブラックサンダーとはなまるうどんの初のコラボレーション、面白いですね!バレンタインデーにはなまるうどんで味噌バターフェアうどんを食べて、オリジナルパッケージのブラックサンダーをもらえるというキャンペーン、楽しみです。さらに、ブラックサンダーを天ぷらにした「ブラックサンダー天ぷら」も気になります。ユニークなアイデアで、食べてみたいです!
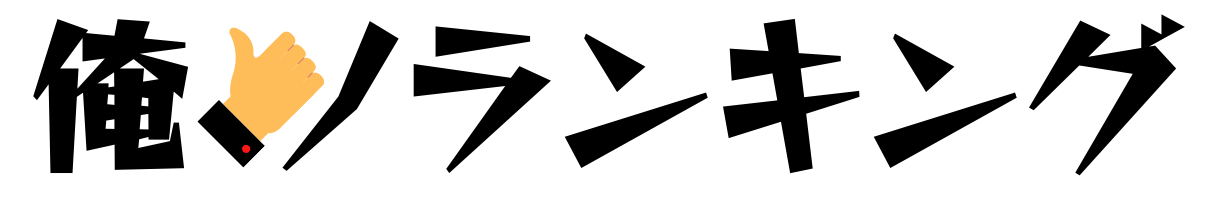













吉野家ホールディングスが一次救命処置講習会「命のバトンプロジェクト」を定期的に開催している取り組みには、地域社会への貢献意識が感じられます。従業員全員が救命処置の知識を身につけることで、緊急時に迅速かつ適切な対応ができるようになることは、周囲の人々を守るために重要な取り組みだと感じました。地域社会における企業の役割を果たす一環として、このような活動が行われていることに感心しました。